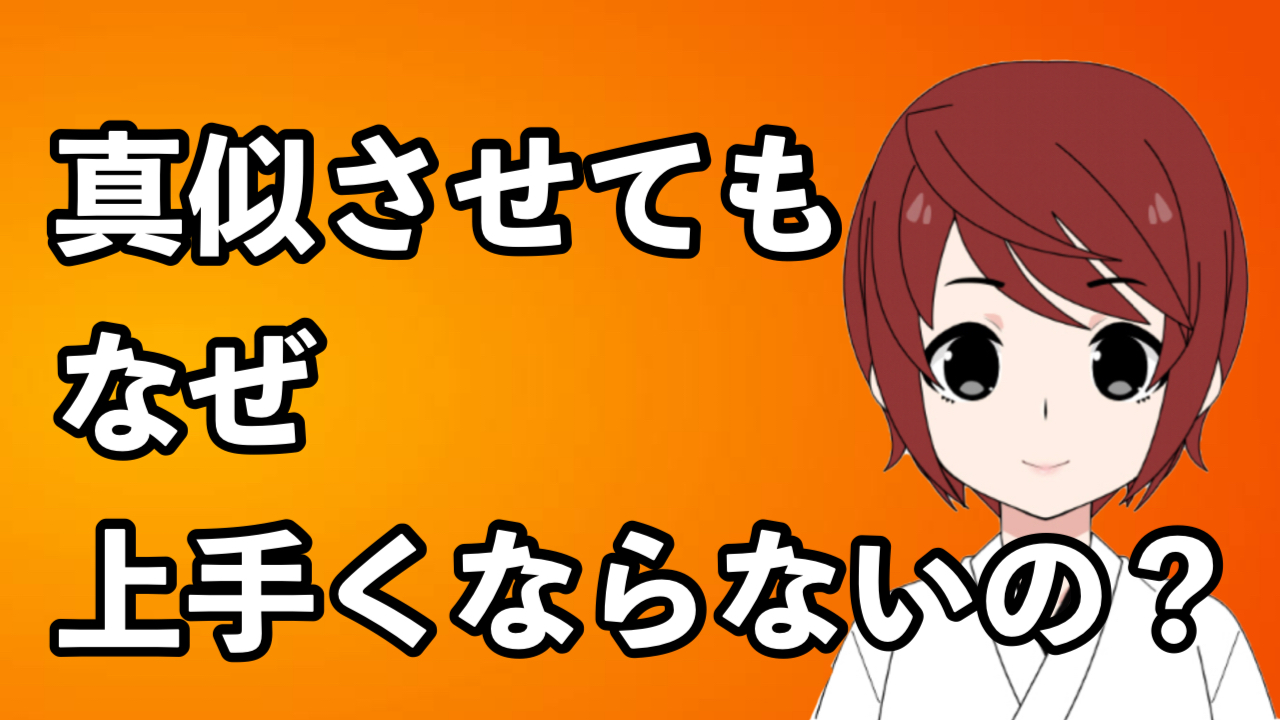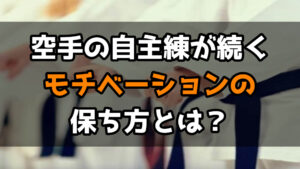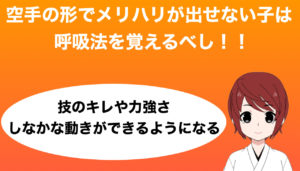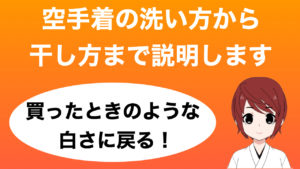こんにちは
めぐ@丁寧な空手家育成教室(@karateOlympic)です。
今回は、道場の先生から上手い人の動きを真似しろと言われたときにやってしまいがちなミスについて話していきます。
うまい人の真似をしようと聞くと、日本代表選手の練習方法や動き方を真似させてしまうお母さんも中にはいます。
実際あなたも日本代表選手の動きをお子さんに真似させてみよう!と思いませんでしたか?
だけど実際、日本代表選手の動きを真似させてもお子さんは上手くなれません…
日本代表選手って自分なりの組手スタイルを自分で作っているのであなたのお子さんが真似するのにはハードルが高すぎるんです。
実際に私も生徒に教えているので、わかるんですが骨格の作りが違えば、身体の使い方も変わってくるんですよね。
だから実際にお子さんに
[word_balloon id=”unset” src=”https://megublog01.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_7547-273×300.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]日本代表選手の動画見せて真似させていますが
上手くなれませんでした[/word_balloon]
っていうお母さんがたくさんいたんです。
先生にすぐに聞けないしこれでいいの?って不安になりながらもお子さんに教え続けていますよね?
自主練になるとどう教えたらいいのかわからないし
何を練習させたらいいのか全くわからなくなってしまう。
でも、本来自主練で何を練習させたらいいのか全くわからなくなってしまうということはありえないはずです。
だって自主練って道場の練習でできないことを、できるようにするために練習するんですよね?
あるいはもっと技を磨きたいから練習しますよね。
こう考えてみると
自主練ってシンプルじゃないですか!
じゃあなぜお子さんが練習しているのに上手くなれないのか?
それはすごいシンプルなのですが、上手い人の真似をするところ間違えてしまっているんです…
空手をやったことのないお母さんが、観たままの練習方法をお子さんに真似させても上手くはなりません。
もし上手くなっているのであれば道場に通わせる必要はなくなりますよね?
ただこういう話をすると
[word_balloon id=”unset” src=”https://megublog01.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_7550-e1593657483884.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]練習方法を真似するんじゃないんだったら、上手い人の考え方を真似しないさいって言うんでしょ?[/word_balloon]
と思う方もいると思います。
確かに日頃から私は考えながら練習しなさいと言っているので、上手くなるためにも考えながら練習しないといけないのは間違いありません。
むしろ、思考停止で試合に出ても試合で勝てるようにはなりません。
だから、上手い人の考え方も学ぶのもめちゃくちゃ大事なんですよ。
ただこの記事を読んでくださっているあなたへ。
道場の先生も教えてくれないお子さんを教える上でいちばん大事なことについて話していきます。
今回の記事では上手い人の何を真似すればお子さんが上手くなれるのか?
道場の先生も気づいていない内容をお話していきますので最後まで見てくださいね。
今回の記事ではこのような3つの構成でお話していきます。
上手い人の何を真似すればいいのか?
まず1つ目、お子さんが上手くなるためには一体上手い人の何を真似すればいいのか?
結論から言うと上手い人が日常生活でどんなことをしているのか。
その習慣を真似することです。
上手い人の習慣というと、朝何時に起きて何をしているのか?
普段どんなふうに生活をしているのか?
道場の間までに何をしているのか?
どれだけ自主練に費やしているのかまで、本当にいろんな習慣を徹底的に真似していきます。
その真似する際には
[word_balloon id=”unset” src=”https://megublog01.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_7550-e1593657483884.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”think” balloon_shadow=”true”]なんでこんな習慣をしているんだろう?[/word_balloon]
と理由を考えながら真似してほしいんですよね。
これは実際に私も小学生の時に先輩にやってみろって言われて先輩の習慣を全部真似していたんですよね。
そうすることによりなんで先輩がそういう行動をとっているのかがわかるようになったり、この練習をすることによりこういう効果が発揮されるんだ!
っていう練習の目的が自ずと見えてくるようになったんですよね。
だからとにかく上手い人を真似させる場合は習慣から徹底的に真似させてみてください。
今回の内容で結果が出る理由

では次に2つ目、なぜ今回の内容を覚えることでお子さんが試合で勝てるようになるのかについて説明します。
試合で勝てるようになるためには、上手い人が行っている練習方法ではなくて習慣を真似しましょうという話ですがなぜ習慣を真似する必要があるのか?
それは練習方法を覚えたところでみんな継続できないからなんですよ。
結局のところ試合で勝てるようにならない子って練習方法がわからないからではなくて上手くならない時に身についた習慣が変わらないから上手くなれないだけなんです。
だって今までを振り返ってみてほしいんですが
普段、生活の中で空手の練習を毎日する習慣ってないですよね?
道場の練習がない日って他の習い事をしたり友達と遊んだり家族と一緒に過ごすじゃないですか?
子供たちの好きなことをさせて過ごさせているじゃないですか!
試合がない、土日に練習することって正直少ないですよね?
私も正直いって土日まで練習する子供ではありませんでした。
土日はゲームや友達と遊んでいましてお子さんもこんな感じですよね?
その習慣がすでについてしまっているのでいきなりお子さんに上手い人の練習を徹底的に真似させようとしても、結局休みの日は練習モードにはならないんですよね…
お子さんがノリ気ではないのに、練習に誘ってもダラダラしたら練習になるじゃないですか?
そして、お母さんかお父さんのどちからかが、お子さんのダラダラしている姿をみてブチキレてしまう。
あなたもこんな経験をしたことはありませんか?
しまいには親子喧嘩をしてしまい、雰囲気が悪くなってしまいお子さんが拗ねてその場から居なくなってしまう。
それだったら最初から練習させない方が良かったと反省することってあると思うんですよね。
そこで、親のやる気と子供のやる気が一致していないということに気がつくんです。
でもこれって非常に難しいですよね…
私も親と練習すると上手くできないところを何度も注意されているうちにだんだんイライラして八つ当たりをしてしまったこともあります。
だからあなたの気持ちも
お子さんの気持ちもわかります。
なかなか親の思い通りに子供は動いてくれないですよね。
でもこれは指導者側も悪いと思っていて、生活習慣を直そと教えてくれないのも問題だと思っています。
だって、練習だけ教えて後は自分で頑張ってねと言われても試合で勝てるようにはなりませんもん。
私もこれまで空手を15年間続けてきた中で、練習だけを教えて試合で勝てるようになった子は見たことがありません。

だから結局のところ普段の生活から、習慣を変えていかないと上手くいかないんですよね。
私はたまたま無意識だったのですが仲良くしている先輩になんでも聞いていたんですよね。
[word_balloon id=”unset” src=”https://megublog01.com/wp-content/uploads/2020/03/Megumi.jpg” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]学校でどんなことをしているんですか?
自主練って何しているんですか?
休みの日に練習するなら誘ってくださいよ![/word_balloon]
ってとにかく何でも聞いてたんですよね。
その中で特に私が印象に残っていることは練習メニューは全部自分で作っていると言うことでした。
一個上の先輩なんですがなんでも自分でやっていることに驚いたんですよね。
その先輩言わく、試合の動画を振り返り自分に足りないところをちゃんと自分で見つけて練習しているよ!って教えてもらいました。
実際に上手い人が何気なく行っている、生活習慣を真似するだけでお子さんは上手くなれます。
低学年の子に自分で自主練のメニューなんて作らせないですよね?
だけど低学年から自分で考えて自主練のメニューを作らせていると勉強の計画も自分で立てられるようになるんです。
お子さんを試合で勝たせたいと願うのであれば習慣から変えることです。
私はずっと空手を続けてきましたが毎日自主練のメニューは自分で決めていましたし自主練をしないと気持ちが悪かったんですよね。
それほどまでに自主練をするのが当たり前だという習慣を身につけると本当に1ヶ月でお子さんは上手くなれます。
よくある行動心理学では、人は21日間行動すると習慣化すると言われています。
上手い子の習慣を真似して21日間だけ続けてみたら30日もかからずに上手い人の習慣が身につきますよ!
再現性があるかどうかを私の教えている生徒の6歳の女の子にも試してみたんですが、実際にその子も21日間で自主練が継続できるように今では、朝練、夕練を毎日頑張っていますし空手日記も毎日書いて毎日LINEで報告をしてくれます。
オフ日は、日曜日だけと言っていました!
6歳の女の子がここまでできるようになっていますので、あなたのお子さんも絶対できるようになります。
やり方をスッテプで説明
最後に3番目。
ステップで、今回の記事を読んで実際に何から始めていけば良いのかについて解説をしていきます。
まず1つ目。
上手い人の習慣を真似する必要があると言うことをお子さんに伝えてください。
次に2つ目。
上手い人がどんな自主練をしているのか?
道場の中に上手い子がいたら
その子に聞いてみてください。
そして3つ目。
あなたのお子さんの
1週間のスケジュールを立てることです。
そして4つ目。
「あとでいいや!」って思ってしまう方って
結局やることを忘れてしまい行動しないんですよね…
後回しにしてしまう癖をここでなおしていかないと何をしてもうまくいかないので、お子さんに今すぐ伝えてください。
この流れで行動すると1ヶ月でお子さんは激変します。
何度も言いますが、上手い人の練習を真似することももちろん大切なんですがそれ以上にまずは、上手い人の習慣を真似すること。
まずは、これを行ってくださいね。
最後に
ここまで読んでみてどうでしたか?
普段道場の先生ってここまで教えてくれないと思うんですよね。
でもそれって、教えてくれないのではなく、「教えられない」のです。
だから結局、あなたが空手の知識をつけていき、お子さんのサポートをしていかないと、先生は教えてくれないので、先生に頼りっきりではダメなんですよね。
そうやって悩むお母さんたちを、私はたくさんみてきました。
だから、この記事が少しでも、あなたの役に立っているのではあれば幸いです。
それでは今日は、以上にします。
最後まで読んでくださりありがとうございました。